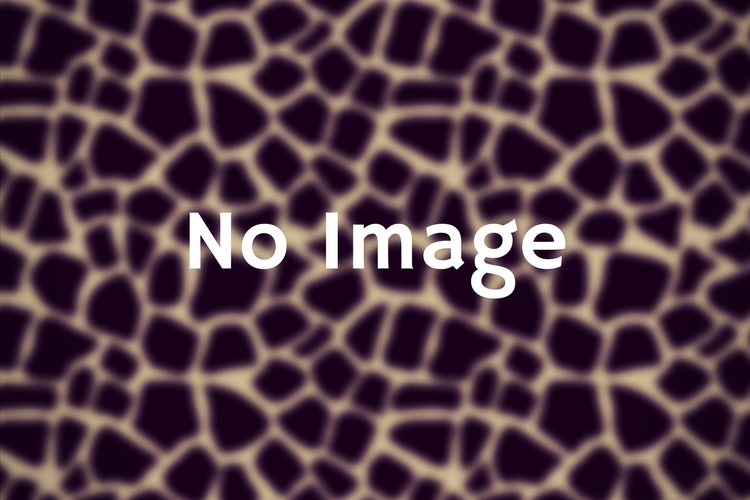過去の耳コピを振り返ってみた(2015年頃のもの)

どうも、杉本卓哉です。
今回は今までにやってきた耳コピを振り返ってみようと思いました。
そんなわけで耳コピについての動画を撮ってからこの記事書いてみることにしました。(記事の最後にも動画のリンクを貼っています)
耳コピをする理由として思いつくこと
耳コピをする理由として思いつくことは、興味を持った楽曲の
・アレンジ的な構造を把握したい。
・コード進行がどうなっているのか確認したい。
・どのようにミキシングしてるのか調べたい。
・新しく買ったプラグイン又は音源を試したい。
・今まで勉強してきた知識などを試してみたい。
これらのことが一気に調べられたり、自分の今のDTM力を試す良い機会だなぁとおもっています。
ゲーム感覚でサクサクやるのが楽しいですね。
記事の最後に貼ってある動画の中ではある程度出来の良いもの選んでみましたが、サビだけ耳コピや、Aメロだけ耳コピなど部分的な耳コピもよくやります。
耳コピの手順
・曲のBPMを調べる
・曲のキーを調べる
・イントロ、Aメロ、Bメロ、サビなど、マーカーを入れて大体のセクションを確認する
これらの下調べをしてから、ドラム→ベース→ボーカル(インストだったらリード)→コード楽器→FX関係の順に入れていきます。
ベース、ボーカルを先にやる事でコードを推測しやすくなります。
ドラム作りでは、音選び、レイヤリング、EQなどの作り込みを細かくやっていきます。ドラムの作り込み具合でクオリティーに大きく影響するからです。
例えば、キックを作っていく場合は、お手本の曲の中で、キックだけ聞こえているところを見つけ、有ればその部分を聞いてそのキックそっくりになるように作り込んでいきます。
もし、キックだけ聞こえる所が無ければ、なるべく音が重なっていないところを探します。
耳コピの再現精度を高めるには、お手本となる音をはっきり聞き取ることが重要だと思います。
バンドパスフィルターなどを使って他の音を取り除いて聞き取りやすくするなどの工夫をしてあげると良いでしょう。
このように、各パートを丁寧に作り込んでいきます。
現時点で自分が持っている技術や知識を最大限に発揮するのがポイントです。(かつ、短時間で終わらせるように気をつける)
打ち込みが大体終わったら
打ち込みが大体終わったらミキシングをしていきます。(できれば各トラックを、オーディオデータで書き出してからミキシングしたいところですが…)
さらに細かくやりたい時は、楽曲の周波数帯域ごとの聞こえ方もコピーしていきます。マルチバンドコンプレッサーなどを使い、お手本と比較しながら調整していきます。
マスタリングの実験や勉強した知識を試していき、データを取っていきます。
ここまでくると、マスタリング的な工程になります。
オリジナル曲でマスタリングするのとは違い、『お手本の曲』というゴールがはっきりしているので、迷子になる心配は無く、マスタリングの実験・練習ができるところが良いと思います。
2015年の頃はマスタリングの細かいところまで目を向けれていなかったのでozoneなどのプリセットを利用していました。
全ての工程が終わったら
耳コピが終わったプロジェクトは、改めてアナライザーなどを見ながらオリジナルと比較して聞いてみて、どこが上手くいったのか?どこが上手くいかなかったのか?などを分析して、今後の作曲のためのデータとして活用します。
ここ最近はiZotopeの“TONAL BALANCE CONTROL”に通して見るのが気に入っています。
いつも400Hz辺りが足りなくなるなぁなどの発見があります。
それらの出来上がったプロジェクトはオリジナル曲を作るときのテンプレートとして利用することもあります。
Ableton Liveではプロジェクトに他のプロジェクトのトラックを簡単に取り込むことができるなど、柔軟性の高さが気に入っています。
まとめ
このように、耳コピをすることによって得られることがいろいろあります。
定期的に耳コピをしていくことで、以前にくらべてこの部分は上手くできるようになったとか、この部分は昔の方が上手くできてるから、つぎからはこの部分を注力していこうなど、技術的な事などアップデートしていくことができます。
貪欲にレベルアップに繋げていきたいですね!
それではまた!